令和7年秋季火災予防運動を実施します(11月9日~11月15日)

急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし

2025年度全国統一防火標語をスローガンに11月9日(日曜日)から15日(土曜日)までの7日間、秋季火災予防運動を実施します。
火災予防運動の目的

火災の発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、火災や火災による死傷者の発生を防止させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的として火災予防運動を実施します。
特に、秋季火災予防運動では、次の項目に重点を置いています。
1 重点推進項目
- 地震火災対策の推進
- 住宅防火対策の推進
- 林野火災予防対策の推進
2 推進項目
- 事業所等における防火安全対策の徹底
- 製品火災の発生防止に向けた取組みの推進
- 多数の観客等が参加する行事に対する火災予防の徹底
- 乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進
- 放火火災防止対策の推進
重点推進項目
1 地震火災対策の推進
地震火災を防ぐため感震ブレーカーを設置しましょう。
感震ブレーカーとは
地震の揺れを感知して電気を自動で遮断する機器で、地震の際の通電火災(停電が復旧したときに発生する火災)を防ぐためのものです。
詳しくは次のリンクから確認してください。
2 住宅防火対策の推進
住宅火災を防ぐため、「住宅防火 いのちを守る 10のポイント(4つの習慣 6つの対策)」を守り、火災を防ぎましょう。

4つの習慣
- 寝たばこは絶対にしない、させない。
- ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
- こんろを使うときは火のそばを離れない。
- コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

6つの対策
- 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。
- 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。
- 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。
- 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
- お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
- 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。
3 林野火災予防対策の推進
全国的に山火事などの林野火災が多く発生しています。紅葉シーズンにより登山を楽しまれる人も多くいらっしゃるため、火の取扱いには注意し、次のような林野火災予防対策をとりましょう。
- たばこのポイ捨て、歩きたばこは絶対にやめましょう。
- たき火やカセットこんろなどの火気使用時は必ず消火準備をしましょう。
- 林野所有者は林野の適切な管理に努めましょう。
推進項目
1 事業所等における防火安全対策の徹底
不特定多数の人が出入りする建物は、火災が発生した際、人命危険が高いため、次のような対策をとりましょう。
- 消防計画に基づく、消火、避難訓練等を実施しましょう。
- 出入口、避難通路などを点検し、避難上支障のある物品は除去をしましょう。
- 消防用設備等を点検し、適切に維持管理をしましょう。
- 出火又は延焼拡大を防止するため、防炎物品(燃えにくいカーテン・じゅうたん等)や防炎製品(燃えにくい寝具等)を使用しましょう。
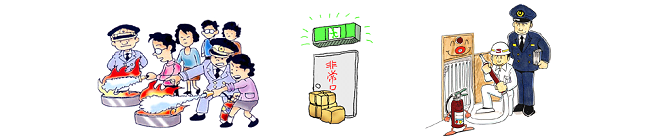
2 製品火災の発生防止に向けた取組みの推進
リチウムイオン電池からの火災が急増しています。
リチウムイオン電池を使用した製品の取扱いには特に注意し、製品火災の発生を予防しましょう。
詳しくは次を確認してください。

3 多数の観客等が参加する行事に対する火災予防の徹底
秋祭り等、多数の観客等が参加する行事は、火災が発生すると被害が大きくなる恐れがあり、火災予防対策が必要です。
- ガソリン等の危険物を取り扱う場合は、離れた場所にある火気、静電気等でも容易に火災に至る危険性がありますので注意しましょう。
- ガソリンの保管は、消防法に適合した金属製容器で行いましょう。
- ガソリンの容器を空ける時は、圧力調整弁等の操作を行い、吹きこぼれないように注意しましょう。

4 乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進

これから冬にかけて空気が乾燥し、火災が発生しやすくなる季節です。
暖房器具、厨房設備などの火の取扱いには十分注意しましょう。
この季節はたき火等による火災が多く発生しています。屋外で火気を扱う際は、下記の項目に注意しましょう。(一部の例外を除き、原則屋外でのごみ等の焼却は禁止されています。)
- 強風時には行わない。
- 消火器等を用意する。
- 一度に多量に燃やさない。
- 火気取扱い中はその場から離れない。
- 付近の住民の迷惑とならないよう注意する。
- 必ず火が消えたことを確認する。
5 放火火災防止対策の推進

放火火災を防ぐため、家の周りには燃えやすい物を置かない、ゴミは決められた日の朝に出すなど放火されない環境作りはもちろんのこと、自動車や自転車のボディカバーを防炎製品(燃えにくいもの)にする等の対策をとりましょう。
放火防止対策 『“ストップ!ザ・放火”』
- 家のまわりに、燃えやすいものを置かない。
- 暗がりを無くす。

火災はちょっとした不注意や不始末から発生します。火の取り扱いには十分注意し、大切な命や財産を火災から守りましょう。
※使用しているイラストは全国消防長会及び総務省消防庁の広報素材を使用しています。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
予防課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9117(予防班)
電話:042-751-9133(消防設備班)
ファクス:042-786-2472
予防課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム








