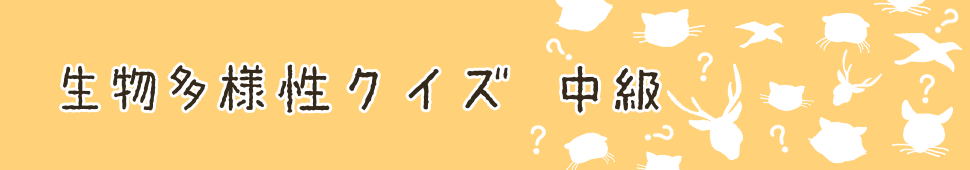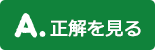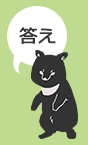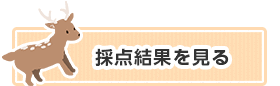1.国の天然記念物に指定されるミヤコタナゴが卵を産むのは次のうちどれでしょう。
1.国の天然記念物に指定されるミヤコタナゴが卵を産むのは次のうちどれでしょう。
正解は の二枚貝です。
の二枚貝です。
ミヤコタナゴは二枚貝に卵を産みます。また、二枚貝の幼生はヨシノボリなどの小魚に寄生し成長します。このように生き物同士は繋がりあっています。環境を守っていくためには生物の多様性が大切です。
 2.生物多様性は、「3つのレベルの生物多様性」が様々な形で複合して成り立っています。相模原市にも生息しているゲンジボタルの発光間隔が、東日本と西日本で異なるのは次の3つのレベルの生物多様性のうちどれにあてはまるでしょう。
2.生物多様性は、「3つのレベルの生物多様性」が様々な形で複合して成り立っています。相模原市にも生息しているゲンジボタルの発光間隔が、東日本と西日本で異なるのは次の3つのレベルの生物多様性のうちどれにあてはまるでしょう。
正解は の遺伝子の多様性です。
の遺伝子の多様性です。
同じ種(ゲンジボタル)であっても、それぞれの個体や個体群で遺伝子レベルでは違いがあることを「遺伝子の多様性」といいます。
 3.虫のアブとハチは見た目や大きさが似ていますが、ハネの数に違いがあります。アブのハネは何枚でしょう。
3.虫のアブとハチは見た目や大きさが似ていますが、ハネの数に違いがあります。アブのハネは何枚でしょう。
正解は の2枚です。
の2枚です。
アブのハネは2枚です。4枚のハネを持つハチは空中で止まることが出来ます。また、アブは毒針を持ちません。
 4.生物の生態系を維持していくうえで重要な「キーストーン種」と呼ばれるはどのような種でしょうか。
4.生物の生態系を維持していくうえで重要な「キーストーン種」と呼ばれるはどのような種でしょうか。
正解は の数は少なくても、生態系に及ぼす影響が大きい種です。
の数は少なくても、生態系に及ぼす影響が大きい種です。
生き物同士の食物網は複雑な関係で成り立っています。例えば、ラッコはウニを食べ、ウニは海藻を食べます。ラッコがいなくなると、ウニが増え海藻が過剰に食べられてしまいます。海藻が無くなると、魚の隠れる場所が無くなるなど環境の変化が発生します。この場合、ラッコがキーストーン種になります。
 5.次のうち河川で生まれた後、海で生活し、河川へ戻ってくる魚はどれでしょう。
5.次のうち河川で生まれた後、海で生活し、河川へ戻ってくる魚はどれでしょう。
正解は のアユです。
のアユです。
アユは河川で生まれたのち、海で生活し、河川へ戻って産卵をする回遊魚(両側回遊)です。
 6.次のうち絶滅が危惧されている植物は次のうちどれでしょう。
6.次のうち絶滅が危惧されている植物は次のうちどれでしょう。
正解は のカワラノギクです。
のカワラノギクです。
カワラノギクは全国でも一部の地域にだけ生育する、絶滅危惧種です。 相模原市は神奈川県の中でカワラノギクが生育する貴重な地域です。現在ではいくつかの地域の河原で市民の手によりカワラノギクをふやす活動が行われています。
 7.帰化植物とはどのような植物のことをいうでしょう。
7.帰化植物とはどのような植物のことをいうでしょう。
正解は のもともと日本にいなかった植物が人の手によって持ち込まれ野生化した植物です。
のもともと日本にいなかった植物が人の手によって持ち込まれ野生化した植物です。
帰化植物とは、本来の生息地から人の手によって他の地域へ運ばれ、野生化した植物です。日本では特に都市部で帰化植物が多く見られます。
 8.健全な森林を育てるために大切なことはどれでしょう。
8.健全な森林を育てるために大切なことはどれでしょう。
正解は の木の密度を調整するため間伐(木を切ること)を行うことです。
の木の密度を調整するため間伐(木を切ること)を行うことです。
健全な森林を育てるには、間伐を行いつつ、伐採した木を木材として利用し、新たな森林を育てる「森林資源の循環利用」をすることが大切です。
 9.生物多様性が生み出す恵みは「生態系サービス」と呼ばれます。「生態系サービス」は4つに分けることができますが、4つのうち「調整サービス」がもたらす恵みはどれでしょう。
9.生物多様性が生み出す恵みは「生態系サービス」と呼ばれます。「生態系サービス」は4つに分けることができますが、4つのうち「調整サービス」がもたらす恵みはどれでしょう。
正解は の森林があることによって気候の緩和や洪水が起こりにくくなることです。
の森林があることによって気候の緩和や洪水が起こりにくくなることです。
森林があることで安定した水を確保できたり、土砂災害の防止や河川の氾濫を防ぐなど、私たちの暮らしの安全を支えています。
 10.アリやハチなどの昆虫は分業することで、効率的に集団をつくります。このような昆虫を何というでしょう。
10.アリやハチなどの昆虫は分業することで、効率的に集団をつくります。このような昆虫を何というでしょう。
正解は の社会性昆虫です。
の社会性昆虫です。
アリやハチなどの社会性昆虫は、集団の中で繁殖に特化する女王と採餌などを行う働きアリ、ハチとで分業する効率的な社会構造をもちます。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。